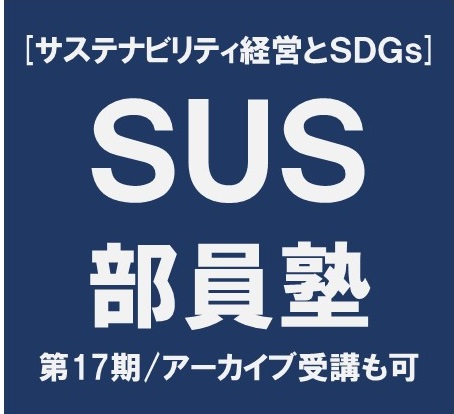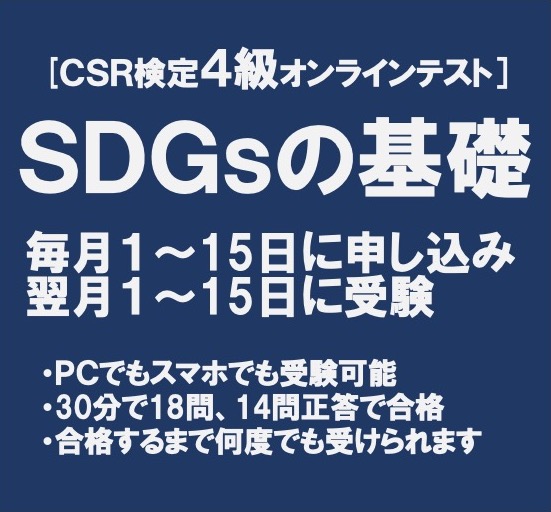日本のフードロスは632万トン(2016年、農林水産省調べ)に及び、食料廃棄の量は世界でも最大規模だ。なぜフードロスが起きるのか。生産者と触れ合える収穫祭「東京ハーヴェスト」を主催する高島宏平氏(オイシックスドット大地社長)は、「食への意識があろうがなかろうがフードロスが多く出てしまう仕組みになっている」と指摘する。解決策として、「生産者と買い手のコミュニケーションを増やすこと」と言い切る。(聞き手・オルタナS編集長=池田 真隆)

オイシックスドット大地の高島社長=11月11-12日にかけて六本木ヒルズアリーナで開かれた東京ハーヴェストの会場で
――日本ではフードロスが632万トンを記録するなど、食への意識が高いとはいえません。日本人が食への意識が低い要因はどこにあるとお考えでしょうか。
高島:そもそも意識が要因ではないと思いますね。そもそも、意識があろうがなかろうがフードロスが多くなる仕組みになっています。
店舗はオーバーストア状態でお客さんを奪い合っています。デフレでもあるので、品物をたくさん用意して値段を下げて提供します。その結果、売れるものは売れるし、余るものは仕方がないという商売をしています。誰も意識が低くて、悪気があってそうしているわけではないと思います。
ただ、事業をやっていて思うのは、一つの大きな課題として、作り手と食べ手の距離が遠いことがあります。これだけ食材が余っているにも関わらず、欲しいものがないことがある。
一方、生産者はどの時期にどういうものが望まれているか分からないから当てずっぽうになります。そうなると、外れることを避けるために、いろいろ多めに作っておきます。
このように、ぼくらは生産者と消費者の間にいるので、両者のコミュニケーションが不足していることで起きるフードロスを目にしてきました。

生産者自らが食材のおいしさを説明する
――生産者が消費者の気持ちを知らない背景には何があるとお考えでしょうか。
高島:生産者はスーパーのバイヤーや農協、自治体の関係者とは話しをよくしますが、案外食べる人と話す機会は少ないと思います。そもそも、買い手の気持ちを知らなくても仕事が回るような仕組みにもなっています。
そうして、一番分かりたいことが分からないまま生産をして、フードロスを出してしまう結果になっています。生産者と買い手が話し合えれば、時期ごとに欲しい食材の量が分かるようになり、フードロスもなくなっていくと思います。
――生産者と消費者の距離を近づけるにはどうすれば良いとお考えでしょうか。
高島:リアルでもネットでもどちらでもいいのですが、とにかくコミュニケ―ションを取る機会を増やすことですね。
本業ではコミュニケーションを仕組み化したビジネスモデルを展開していますが、東京ハーヴェストではまだビジネスモデルはないです。ですが、ここで出会って畑に行っているお客さんもいると思いますので、自然と新たなビジネスモデルが生まれていくはずです。

ロート製薬が販売する糀(こうじ)発酵飲料「Jiyona」は、種子島の在来種「一吉紫芋」を使用
――東京ハーヴェストは今年で5回目を迎えました。このイベントを通して、生産者と買い手の距離を近づけています。手応えはどうでしょうか。
高島:東京は世界で最もおいしい料理が食べられる都市の一つだと思いますが、その食文化はシェフとつながっていて、生産者をリスペクトする機会はなかなかないと感じていました。
世界の食の都市では、シェフだけでなく、作り手をリスペクトして、食文化を広げています。
持続可能な文化にしていくためにも、生産者をリスペクトする機会をつくりたいと思いました。また、パリでは農業祭が、スペインではトマト祭りがあるように、世界を代表する食のイベントがあり、日本を代表する収穫祭をめざし、この活動を始めました。
最初の頃は集客にも苦労しましたが、いまでは大規模な告知をしなくても4万人もの人が来てくれるようになりました。出展者からも消費者と触れ合うことを楽しみにしているという声を聞くので、手応えを感じています。
六本木で行っているので、外国人観光客が多く訪れます。2020年の東京オリ・パラに向けて、日本の食を多面的に発信する良い機会になるとも考えています。
――東京ハーヴェストではKPIなど目標は設定していますか。
高島:KPIはないですね。もちろん、本業はKPIを持ってやるべきですが、有志の任意組織で行う場合、厳しいKPIを持ち過ぎるとスタッフの気持ちが荒んでしまうことを恐れています。ボランタリーに行うことは、関わる人の気持ちがサステナブルではないと続かないと思います。
来場者数や売上高よりも、スタッフが楽しめたかどうかが大事。「来年はこんな企画をやりたい」と言ってくるかどうかを重視しています。

会場内に用意されたテーブル席には食材が並べられている。作られた料理だけでなく、食材一つひとつにも目を向けてほしいとの思いから
――2000年に創業し、当時契約した農家は20件あまりでしたが、今では大地を守る会とも経営統合し、2700件にもなりました。利益追求と社会貢献を両立するためには、どのような考えを大切にして会社を経営してきましたか。
高島:利益追求を考える時、お客さんと生産者と自社の3者の利益追求になっていないといけません。利益追求と社会貢献の両立というと、ついつい会社目線になりがちです。それだとサステナブルではないと思います。関わっているステークホルダー全員に対して、ウィンウィンウィンになるビジネスモデルを追求してきました。
ですから、自社の利益を追いかけるのではなく、全体の社会の仕組みとして、みんなが喜ぶためにはどうすれば良いのかという観点から事業を考えるようにしています。
ぼくたちは国内の農業や食品の課題に事業でアプローチしていますが、これらの問題を解決するためには多くの人を巻き込まないと到底実現できません。
ですので、「この食材を食べるべきだ」と一方的に押し付けるのではなく、美味しいから食べ続けて、気付いたら解決していたという方法を選んでいます。
安全で美味しい食卓は、健康にするだけでなく、例えば、離婚を減らして、子どもを増やすことにも貢献すると思います。平和への近道は食卓から始まると直感でそう信じています。ぼくらなりの楽しい方法で実現していきたいです。