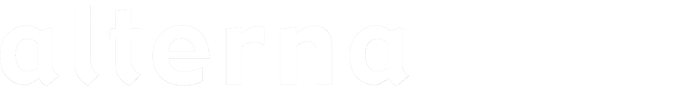今年もたくさん映画を観たが、今年のTOP3に入るのではないかというくらい好きな映画であった。
主人公の下倉幹人さん(16歳)は初演技とのことだが、映画を観ていて「誰も知らない」の柳楽優弥さんを彷彿させた。彼の瞳が、眼差しがこの映画を印象付ける。
この映画はフィクションではあるが、映像のタッチはまるでドキュメンタリーだ。インタビューを読んでいると、福永監督も脚本は書いたが、あまり台詞を覚えさせたり、演出などは入れたりせず自然な様を撮ったという。
冒頭、印象的だったのは北海道 阿寒湖のアイヌ観光地のど真ん中に住む主人公が朝食を一人で食べ終わり、小学校へ行くシーン。
家のすぐ外では観光地らしく、アイヌの町、アイヌの文化についての町内アナウンスが延々とリピートされている。

延々とリピートされるアナウンスからは毎日毎日逃げられないのである。私なら、私が中学生ならこの環境に不快感を持つだろうと思った。
案の定、学校での進路相談のシーンでは「どこに行きたいというのはないが、この町以外がいい」と主人公のカントは言う。母親にもアイヌに嫌悪があることを伝える。
下倉幹人さん自身バンドをやっているが、劇中のカントもバンドをしていて、Chuck Berry のJohnny B Goodeを演奏するシーンがある。
この曲も田舎のギター少年が町を出てスターになっていくような歌詞だ。海外のロックスターに憧れる少年にこの町は狭過ぎたのかもしれない。
実際にアイヌでこの町で活躍している秋辺デボさんが演じる「デボ」と山にキャンプへ行くシーンが印象的であった。
山の入る前のお祈りから、死者の村まで繋がっているという穴、この後説明するイトマンテまで、アイヌの自然に対する敬意というか、「畏敬」の念を感じることができる。自然と密接であるが故に存在する「畏れ」。これは現代の都会人が忘れてしまったことかもしれない。
いつしか、自然をコントロールできるなどという過信により、人が一番偉いんだ、という過信により、モノを大切にしなくなり、それが今起きている気候変動や海洋プラスチック汚染、絶滅危惧種の増加、大量の食糧破棄、大量の衣類破棄などのアンサステナビリティな状態に繋がっているのではないかというのは想像できる。
「アイヌはもうアイヌの伝統を引き継ぎきれていない」
さて、先程出てきたイオマンテという儀式がこの映画の大筋になる部分であり、この儀式を実際のアイヌの町でアイヌの人々により映像化させたことにこの映画の歴史的価値があると思う。
「熊送り」と言われるその儀式は熊を神として、もてなし、育て、そして最後は殺してまた黄泉の世界へ帰ってもらう、というものである。
イオマンテにまつわる詳細は割愛するが、いくつか印象的であったことを挙げれば、一つは熊送りのアイヌ語の祈りの譜を暗唱でなく、「資料を見ながら」読み上げている様を映し出す場面。これと同様の場面がイオマンテ前にある。
それはカントのお母さんがお土産屋を営んでいるが、そこのお客さんに「あなたアイヌ?日本語上手ですね!」と言われるシーン。
そのシーンの後にカントのお母さんがアイヌ語をクラスで学ぶシーンが映し出される。
アイヌはもう日本語ではなくアイヌ語を学んでいるのである。
その祈りの譜を、資料を見ながら読み上げる場面とアイヌ語をお母さんが学んでいる場面に共通することは、「アイヌはもうアイヌの伝統を引き継ぎきれていない」ということ。