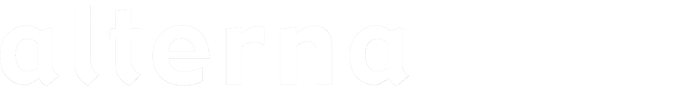肉体的にも精神的にも、そして社会的にも「健康に生きる」、それはすべての人間に与えられた権利であるにもかかわらず、世界を見ると未だ貧困や紛争、社会的差別などさまざまな問題が原因で健康とはほど遠い暮らしを余儀なくされている人たちがいます。40年にわたり、アジアの国々から地域の課題解決に取り組む人を日本に招き、現地での活動に生かしてほしいとリーダーシップを育ててきた団体があります。(JAMMIN=山本 めぐみ)
毎年、アジア各地より10数名の研修生を受け入れ

愛知県日進市を拠点に活動する公益財団法人「アジア保健研修所(AHI)」。1980年の団体設立以降、40年にわたりアジア各地から研修生を受け入れてきました。
「各国の村で活動している現地のワーカー10数名を年に一度日本に招き、リーダーシップ育成のために合宿形式で6週間の研修を行っています」と話すのは、団体事務局長の林(はやし)かぐみさん。
「この6週間は私たちが一方的に教えるというものではありません。極端にいうと何をするのか、そのメニュー作りから研修生の皆さんで作り上げてもらいます。6週間の研修で得たものを国に持ち帰り、それぞれの活動のフィールドで生かしてもらうことを目指しています」
これまで研修を受けた人の数は1,000名を超え、研修後は互いに学び合いを続けるパートナーとして引き続き関係を築きながら、アジア各地にネットワークを作ってきました。
本人の気づきが、成長のきっかけに

6週間の研修では一体どのようなことを行うのでしょうか。
「参加者はそれぞれ国や文化が異なるのはもちろん、活動の内容、背景や課題、解決のためのアプローチの方法も異なります。たとえば児童労働の問題に取り組んでいる人もいれば、女性差別の問題や薬物依存、HIVの問題に取り組んでいる人もいます」と林さん。
「『活動のテーマが全然違うのに、じゃあ何をするの?』と思われるかもしれませんが、表面上は異なる問題でも、根本にある貧困の問題、その構造については、突き詰めて考えていくと共通しているところがあります。意見を交わす中で、自分の活動や視点、思いとは全く違うように感じた相手の意見にも共感したり、共通性を見出したりするようになります。それぞれの活動や自分の目的と照らし合わせながら、研修を進めていきます」
さらに研修期間中、共同生活を送ることで得られる学びもあると話すのは、スタッフの谷村尚子(たにむら・なおこ)さん。

「研修生は6週間、3人一部屋で共に過ごします。あえて違う国、異なる宗教や文化の人同士が同室になるようにしています。共に過ごす日々の中で得る気づきは、その後の活動や人生に大きな力になるからです」
「6週間もあると、少しずつ一人ひとりが生きてきた環境や習慣、文化の違い、それぞれの我も当然出てきます。それを目の前にした時にどのような行動をとるか。相手を批判して終わるのか、受け入れるのか、話し合ってルールを決めるのか…。何が最善ということではなく、本人が『自分はこういう風に思うんだな』といったことに気づき、成長するきっかけにもなります」
「『研修に参加したらこうなる』というわかりやすい成果は挙げづらいところがありますが、大なり小なりの気づきを、その後のそれぞれの活動なり人生なりに生かしていくこと。6週間の研修を通じてその人の中に残ったものが、何かしらその人の活動にインパクトを与えるものになればというのが狙いです」
「私の足を切らないで」。団体創立のきっかけは、ある女性が発した一言

なぜ、この活動を始めたのか。そのきっかけとなったのは、AHI創設者で医師の故川原啓美(かわはら・ひろみ)さん(1928〜2015)がネパールで出会った女性の言葉でした。クリスチャンだった川原さんは、「あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい」というキリストの教えを自らの生き方としても目指したいと1976年、ネパール中部の病院に3ヶ月勤務します。そんなある日、川原さんのもとに二日をかけてある夫婦が診察に訪れました。

「26歳の妻の右膝には大きな腫瘍がありました。診察すると、それは骨まで達しているがんであることがわかり、川原が『命を守るためには、至急右足を切断しなければならない』と伝えると、彼女は次のように答えました」
「『切らないでください。死ぬのは悲しいことですが、私が死ねば夫には新しい妻が来てくれて、夫を助け子どもたちの世話をしてくれるでしょう。でも私が足を切断したら、命は助かっても、家事も何もできない。そうしたら貧しい我が家は全滅するかもしれない。私にはそんなことはできない』と」
自分の命よりも家族を思う彼女の言葉に、川原さんは大きな衝撃を受けたといいます。
「彼女の選択の潔さに触れ、自分の命を犠牲にしても誰かを守りたいという姿勢に川原は『かなわない』と感じたそうです。貧しく弱い立場にある女性、助けるべき相手が、実はこんなにもすごい力を持っていたのです」

「この経験から川原は、人は誰しもに必ず秘められた力や天から与えられた賜物(たまもの)があって、それが引き出されて発揮できるような社会こそ本当の意味での『健康な社会』といえるのではないかと考えるようになったのです。そして帰国後、1980年にAHIを設立しました」
「団体名に『保健』という言葉が入っているので、医療や衛生に関する専門知識の研修をしていると思われることもあるのですが、そうではありません。私たちが意図する『健康』とは、かならずしもそこだけに限らないのです」
「生まれた場所や環境、性別が理由でやりたいことができなかったり、差別を受けたり、生きることが脅かされたりすることがないように。心身ともに健康に、その人がその人の力を発揮して生きていけるように。そのために地域の人たちに働きかける『保健ワーカー』を増やしていきたいのです」
「リーダーシップとは何か」は参加者一人ひとりが見出すもの

「私たちの研修はリーダーシップ育成を目的としていますが、では果たして『リーダー』とは、『リーダーシップ』とは何でしょうか」と二人。
「私たちは研修で、あえて『リーダーシップとは何か』を定義しません。それは研修に参加する一人ひとりが感じ、考えて得ていく答えだと思うからです。参加した一人ひとりが自分たちの活動するコミュニティで力を発揮するために、それぞれ自分にとっての『リーダーシップとは何か』を発見する場になればと思っています」

「研修生はここで学んだ後、自分たちの国に帰り、それぞれの地域社会をよくするために活動していく人たちです。だから、研修中ではどんな場面でも『自分たちの中から声を出してもらう』ことを意識しています。明らかに答えが分かっていたり見えていたりするような場合も、こちらがそれをいうのではなく、とにかく待つこと。進まないように感じる時もとにかく待ち続けて、自分たちの言葉や感覚を見つけてもらうようにしています」
「『自分たちの中から声を出す』ということは、地域社会を変えていく活動の原理だと思います。そうでないと、どこかから誰かがやってきて全部支援してくれたら、その時は一見状況が改善したように見えても、長続きしません。持続可能な支援を考えた時に『自分たちがどうしたいか』『どういう方法ならできるのか』をしっかり考えていく必要があります」
「自分が良ければ良い」では、明るい未来は築けない

「日本で暮らしていると、『途上国』や『貧困国』と聞くと自分とは関係のない世界のことのように感じる人もいるかもしれません」と林さん。
「しかし今の時代、物質的には豊かであるはずの日本でも、皆なんとなく生きづらさや窮屈さを抱えています。『自分だけ良ければ良い』を乗り越えて違いを受け入れ認め合い、少しの思いやりを持って接する人が増えていけば、抱える課題が違っていても、日本も途上国も同様に良い方向に向かっていくのではないでしょうか」

「世界の国々が同時に直面した新型コロナウイルスの流行はある意味、世界の構造やあり方を露わにする出来事だったのではないでしょうか。日本でもワクチン接種がスタートしましたが、『誰でも望む人は、ワクチンを接種できる』ということが希望であり理想です。しかし世界的に見ると、裕福な国がワクチンを囲い込み、貧困国には届かない現実があります。ここからも世界のパワーバランスや構造をイメージしていただきやすいのではないかと思います」
「そしてもう一つ、今の状況から学べることがあります。自分はワクチンを打ってウイルスに感染しなかったとしても、町中で感染が広がっていたら、いつまでたっても旅行や食事に出かけることはできません。『自分だけ良ければ良い』という考え方、『自分ファースト』は少しずつ通用しづらくなっているのではないでしょうか」
団体の活動を応援できるチャリティーキャンペーン
チャリティー専門ファッションブランド「JAMMIN」(京都)は、「AHI」と1週間限定でキャンペーンを実施し、オリジナルのチャリティーアイテムを販売します。
4/12〜4/18の1週間、JAMMINのホームページからチャリティーアイテムを購入すると、1アイテム購入につき700円が「AHI」へとチャリティーされ、アジア各地より研修生を日本に招くための資金として活用されます。
「毎年秋に開催してきた研修ですが、2020年はコロナの影響で開催することができませんでした。昨年来日予定だった研修生たちとは定期的にオンラインで集まって研修の準備を進めてきましたが、まだまだ先が見通せない状況が続く中、2021年秋の開催も見送ることにしました。渡航できるようになるまでオンラインで研修を行い、対面がかなうようになったら皆で集まって、それまでの学びをさらに深める機会を設けることができたらと思っています。通常、参加者の渡航費は先方の団体と半々で、ひとり当たり約5~6万円を私たちが負担しますが、次回の開催については、特例として全額私たちが負担することにしています」(谷村さん)

JAMMINがデザインしたコラボデザインには、玉ねぎやカブ、ニンジン、サツマイモ…、太陽の光と土の恵みをいっぱいに受けて元気に育つ様々な野菜を描きました。異なるルーツや背景を持つ者が集まり、時にぶつかったり寄り添ったりしながらも共に成長する、AHIの研修を表現しています。
チャリティーアイテムの販売期間は、4/12〜4/18の1週間。JAMMINホームページから購入できます。
JAMMINの特集ページでは、インタビュー全文を掲載中!こちらもあわせてチェックしてみてくださいね。
・生まれた場所にかかわらず、その人の持つ力が最大限に引き出される健康な社会に向けて。課題解決のためのリーダーシップを育てる〜公益財団法人アジア保健研修所
JAMMINの企画・ライティングを担当。JAMMINは「チャリティーをもっと身近に!」をテーマに、毎週NPO/NGOとコラボしたオリジナルのデザインTシャツを作って販売し、売り上げの一部をコラボ先団体へとチャリティーしている京都の小さな会社です。2014年からコラボした団体の数は350を超え、チャリティー総額は5,500万円を突破しました。